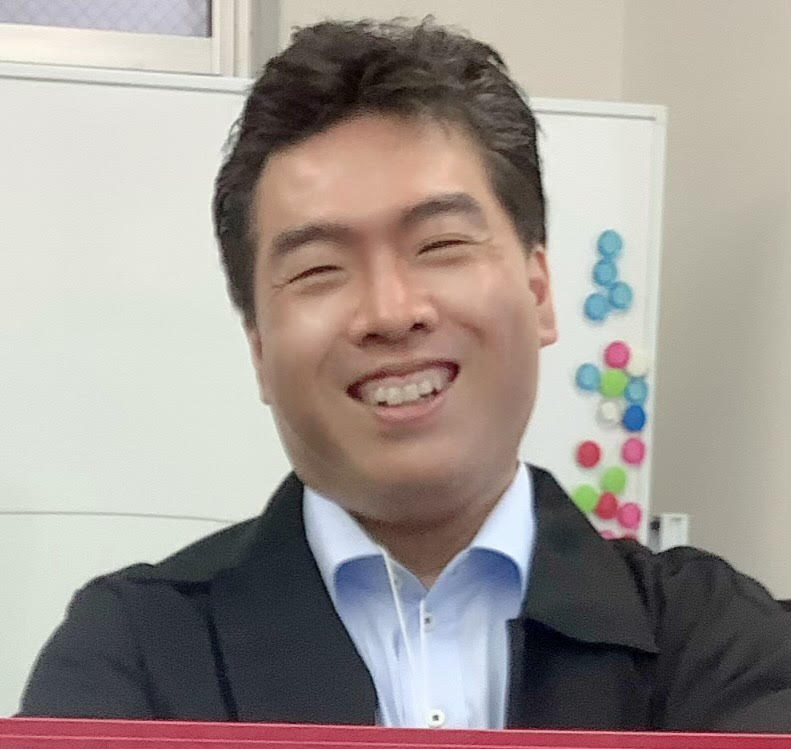いとテラスcafé 始まります!
いとテラスcaféは、私いとやんがご紹介したい毎回各分野でご活躍中だったり、興味がひかれる活動をされていたりする人物に光をあて、鋭く迫る至高の一時間です。
イメージ的にはラジオ放送のように、暖かい飲み物を飲みながら。
また、ゲストの方に質問をするなど参加の仕方はなんでもOK!
人それぞれ感じ方は違うかと思いますが、あなたが初めの一歩を踏み出すきっかけになり、多様な人や分野とつながるお手伝いをする機会をワークショップを通じて創り出すことが、私にとってのミッションであると考えています。
おそらくONtheUMEDAの企画史上、ダントツの緩さと自由度でみなさんをお迎えいたします(周囲の人への迷惑や進行上の妨げにならなければなんでもOKです)
今回のゲストはカウンセラー/自動車整備専門学校講師 木林小和(こばやしこより)さん おはなしすごろく考案の背景を語ります!
(いとやん:以下いと)今回のいとテラスcaféゲストは木林小和さんです。普段のいとテラスとは異なり、トーク場面は30分に圧縮しますが、後半は「おはなしすごろく」を実際に体験していただけます。小和さん、まずは自己紹介いただいても構いませんか?
(木林小和さん:以下木林)私は自動車整備士専門学校で講師をしています。担当の授業において、生徒のメンタルがつぶれないようにオリジナルの授業を行っています。一見遊んでいるようですけれども自分の気持ちを表現したり、思っていることと気持ちを相手に伝える前に自分が何を思っているのかということを整理したりすることを目的に作りました。遊びながら自己開示や対話を目的にワークショップも開催しています。
(いと)時間の関係で深くは掘り下げられませんが、普段はどんなことをされていますか?
(木林)ふだんはこのおはなしすごろくを大人向けに平日の夜や土日を使ってやりますと告知し、口コミで集まってくださることが多いです。またすごろくのボードの質問事項には裏に磁石が貼っていますので、小学生や中学生向けに質問内容を変えてワークショップを行うこともできます。
(いと)一見自動車整備士の養成とは関係がないようにも思えるのですが、そこに繋がる理由を教えていただけますか?
(木林)うちの整備学校は2年制で、1年生が夏休みから就活を始めていきます。事前に2年生に「面接でどんな質問をされたの?」と尋ねて、それを1年生にフィードバックしていくんです。ただその質問を事例として紹介するだけでは面白くないじゃないですか。そこで遊びの延長線上で答えられる練習ができればと思い、実際に大手の自動車会社での面接で交わされた質問をもとにおはなしすごろくを作成しました。でも内容としては「どんな人間になりたい?」とか「10年後どうなりたい?」など固くなりがちなので、最初の方は「好きな食べ物は?」とか「どんな部活していた?」といったカジュアルな質問を充ててお互いを知るための雑談の延長線として話題をおくと、とっつきやすいかなと思ったのがきっかけです。最初は考えてもいなかったのですが、大人向けに質問事項を作ってやってみた方が盛り上がるのではと思い、質問の幅も広げてワークショップも始めていきました。
(いと)担当されている生徒さんは外国から来られた方が多いということでしたね。
(木林)一クラスで40名ほどいるのですが、だいたい30名ほどが留学生でメインになっています。
(いと)そう言えば、英語も指導されておられるって話でしたよね?
(木林)はい、別学科なのですが、英語の授業を受け持っています。英語は正直できないのですが、授業では英語も使いますが、テーマを決めて日本語でグループトークをするスタイルです。英語の堪能な留学生が何人かいますので、「これって英語でどう言うの?」などと尋ねながらやっています。人種や国籍を越えて交流を深めることもそうですが、ここでも対話をするなかで自己開示ができることを目的としています。
(いと)これって会話のきっかけにもなりますよね。海外から来られた人はもちろん、日本にずっと住んではいるけれども会話慣れしていない若い生徒さんなど「そうだね…」だけで終わることも少なくないのでは?そこでおはなしすごろくをきっかけに生徒が変わりだしたというエピソードを聴きたいのですが、いかがでしょうか?
(木林)もちろん全員がグループワークに向いているわけではありません。最初は自分が答える番が来ても「パス」ばかりする生徒もいました(笑)でも輪に入っているだけでも参加しているってことなので他の人の意見を聞いてくれたらいいよと言ってあります。授業の最後には振り返りシートを箇条書きで書いてもらうのですが、名前のみが記されて白紙で出していましたね。でも回数を重ねるごとに、「こんなことが楽しかった」など一言、二言と増え、最終的に4つまで箇条書きしてくれるようになりました。


おはなしすごろくの持つ絶大な効果!
(いと)すると、普段の対話も変わってきた?
(木林)生徒間同士で見ると4月は立ち上がりの段階で当然お互いのことを知らないし、日本に住んでいた学生からすると留学生がどれだけの日本語レベルかわからないのでなかなか話しかけられないんですね。話しかけてもわかってもらえないかもと思うと話しかけることに億劫になっていく。実際は日本語をベースに授業が受けられるレベルの人が集まっているので絶対通じるはずなんですよ。他でアルバイトも積極的に行っていますしね。そこで日本に住んできている学生に話す機会をつくることで、「意外に話せるやん」ということに気付き、「スパナ貸して」ぐらいのちょっとしたコミュニケーションが自然にとれるようになるのを見ると、効果はあったんだろうなと感じています。
(いと)やはり会話の第一歩がなかなか進まないことが問題なんでしょうね。
(木林)受け身で自分から踏み出せることができない子が多いかな。そこまで自分のことを掘り下げて考えることもないし、深く他者とかかわることを避けている印象です。だから自分のことはあまり話さない。留学生には陽気な生徒も多いのですが、彼らと比較すると日本に住んできている生徒は自分が何を考えていて、どう思っているのかがわかっていないことが多いですね。
(いと)それなら、空気を読んで初めの一歩を踏み出せないということとは違う?
(木林)違いますね。だから自分がしんどいのか、わからないのかを周囲に知らせられる人になってほしいということを目的にしています。どうしても整備士業界は離職率が高いんですよね。なにがしんどいのか一つとっても、仕事内容や人間関係など理由はいろいろあるはず。でも、「わからない」としか言わない子が多い。上司が聞いても結果は同じ。それでは自分も会社側も双方困ってしまう。そうなると「誰にもわかってもらえない」と思い込み、負のループに陥ってしまうので何とか食い止めたい。だから自分の気持ちや好みがわかり次のステップでそれを相手に伝えられるトレーニングをしておけば、社会人になっても変わって行けるんだろうなと。
(いと)おはなしすごろくはコミュニケーションツールの一つと思っていましたが、前段階で「自分の殻を破る」ためのきっかけにもなるような気がします。
(木林)そう思いたいですね。例えば「何に今はまっているの?」と聞かれて「Netflixだよ」と答えるだけでも立派な自己開示。普段自分からはなかなか発信できなくとも「Netflixでどんなん見るのが好きなん?」と問われて、「アクション映画かな」と続けるだけでももう二つ、三つは自己開示できていますよね。最終的に相互理解が深まるところまでやっていきたいです。
(いと)いいですね!卒業するときに「おはなしすごろく、良かったよ!」とか言われますか?
(木林)まだ就任2年目ですのでこれからですね。
(いと)そういった声、聴きたいでしょう?
(木林)ええ、役に立っていればいいなと。
(いと)ここでインタビューを引き取ります。ここまでで小和さんに尋ねたいことがありましたらご遠慮なくどうぞ!


活発な質疑応答のコーナー
(参加者)同じメンバーで同じボードを使っているとマンネリ化すると思うんですけれども内容をアップデートしたり質問レベルを少し上げていったりなどしていますか?
(木林)はい、できますよ。アナログですが磁石で質問内容は置き換えられるし、内容もカジュアルなものから面接対応まで幅広いです。大人向けから小学生向けまでいろいろなレベルにわたり、100ぐらいの質問をつくっています。うちの科は40人いるので、4人ずつに分かれても対応できるよう、あらかじめ10シートは用意しています。
(参加者)おはなしすごろくの質問事項で「これだけは残しておこう」というものはありますか?
(木林)後程ルール説明をしますが、「全員答えてね」という質問項目があるんですね。これはその人の価値観に関わるような内容になっています。でもそんなことを一人だけ答えるというのは恥ずかしいじゃないですか(笑)そのなかでも「小さい頃の夢」とか「一つだけ願いが叶うなら…」などは絶対に残しておきたいです!
(参加者)資格試験は日本語で書かれているんですか?
(木林)私もかつて整備士の試験を受け資格も持っているんですが、テストは運転免許と同じで「ある」とか「ない」とかで問われています。文末をいじって、具体的に言うと正誤問題で4択から「あてはまる、もしくはあてはまらない」を判断しないといけないのですが、当然日本語の意味がわからないと答えられないものばかりです。でも留学生でほぼ落ちる子はいませんし、1年次で就職見込みが決まる子も少なくないですよ。
(いと)みなさん、ご質問ありがとうございました!ではこれから実際におはなしすごろくをやってもらうことにしましょう。では小和さん、ルール説明をお願いしますね。
編集後記
いとテラスcaféでは今社会で関心が強まり、注目されているテーマを巡ってたくさんの方からお話を聴いていきます。
小和さんの自己開示が促す熱意と挑戦が会場にいる方にも伝わりその後活発な質疑応答が行われ、ここで新たな得られた学びも少なくありませんでした。
お話を最初に伺ったときに整備学校の授業でなぜ「おはなしすごろくを使っているんだろうか?」というのが不思議でたまりませんでした。
日本にずっと住んできた生徒がなかなか自己開示できないのも「空気を読んで一歩前に進めない」ことが原因ではと考えていましたが、本当のところはその前の時点で躓いていることが少なくなく、不快だとは感じていても「自分がどう思っているのか」、「どうしたいのか」まで考えるまで至っていないことが多いと知り非常に驚かされました。私で言うと心理学のワークショップやカウンセリングなどを行う際の前提が崩れることを意味するからです。
また、日本の現状はこのままでは危ないとも感じました。もちろん生徒によりけりだとは思います。現代の教育で思考力の養成が注目されていますが、自分の意見をアウトプットする習慣を磨く場が思ったよりも少ないのかもしれません。ディベートも大切ですが、もっと手前で雑談ができることやその心理的安全性を確保することも大切です。学校現場でもその必要性は感じてはいるでしょうけれども、社会の中でもおはなしすごろくのような自己開示を育む場が今後もっと必要になってくるはずです。
なお4月に小和さんが書いた『綺麗なんかじゃない』が出版されるとのことです。アマゾンで注文していただくと、本が届けられる仕組みです。
今回は触れられなかったのですが、事前のインタビューの中で「一番尊敬している人は主人です」という言葉が非常に印象に残っています
小和さんのこれまでの波乱万丈な人生を経て、今の活動にどのように繋がっているのか、学生たちの気持ちにより合えるようになったのかがわかる作品かもしれません。
コミュニケーションだけでなく多様な角度から参加者からの質疑応答で活発に行われ、個人的には主催者なのに学ぶことだらけでした…(笑)
日本のコミュニケーションの場を作り自己開示を促す木林小和さんの今後の活躍に注目です!
おはなしすごろく体験会やってみた
後半の体験会では、参加者が全員男性で経歴や世代など多岐にわたっていましたが、おはなしすごろくで会話が深まり終了した時には、今までずっと友人関係を持っていたかのような錯覚を覚えるぐらい自己開示が自然にでき、距離がグッと近くなったような不思議な感覚でした。なお私のお話しグループは一つの質問だけでどんどん話が広がり、ほぼコマを進めていないぐらいでしたよー(笑)